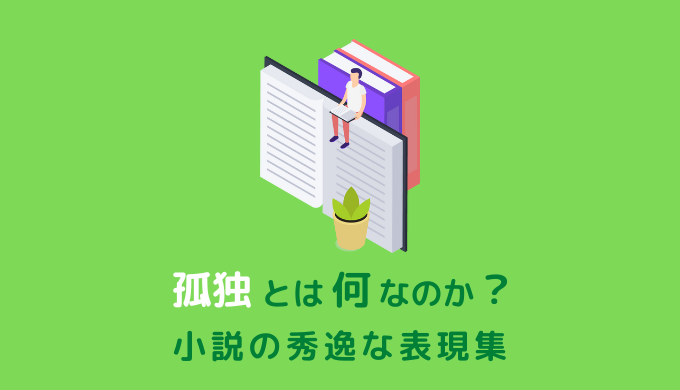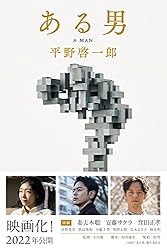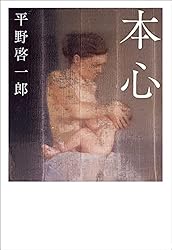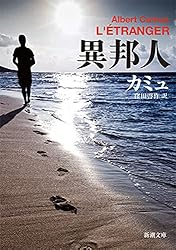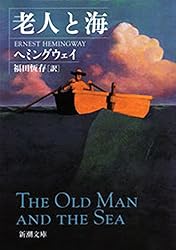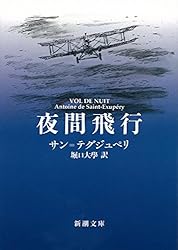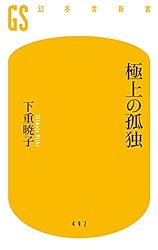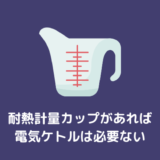孤独は、単にひとりぼっちという状態をさす意味だけではなく、例えばさびしいといった主観的、心理的な意味もあります。
孤独は社会問題化しており、政府も実態把握と対策を進めているようです。
政府調査によると、世代別の孤独感が最も高い30歳台では10人に1人が、孤独感を「常に感じる」との結果になっています。「時々ある」を含めると、2人に1人以上が孤独感を感じていることになります。
内閣官房孤独・孤立対策担当室「人々のつながりに関する基礎調査(令和3年)」より
孤独は、もはや他人事ではありません。
孤独とは何かを知ることが、孤独を乗り越えるための処方箋の第一歩になると思います。
孤独を知るうえで、人の内面や苦悩を言語化し、巧みに表現した小説は貴重なヒントになります。
この記事では、孤独の意味と、小説が教えてくれる孤独とのつきあい方をまとめました。
⼀般的に、「孤独」はひとりぼっちである精神的な状態を指し、 寂しいという感情を含めて⽤いられています。
孤独の辞書的な意味
孤独の辞書的な意味を確認しておきます。
仲間のないこと。 ひとりぼっち。「〜感」
広辞苑
仲間や⾝寄りがなく、 ひとりぼっちであること。思うことを語ったり、⼼を通い合わせたりする⼈が⼀⼈もなく寂しいこと。また、そのさま。「孤独な⽣活」「天涯孤独」
大辞林
孤独の社会的な定義
内閣官房 孤独・孤立対策担当室がまとめた資料によると、孤独には確立した定義が存在しない、とされています。
以下は、「有識者、NPO法人等のヒアリングにおける主な意見等」から抜粋した内容です。
- 孤独、孤立とも確立した定義が存在せず、研究の都度、目的に応じて定義付けしているのが現状。
- 孤独は主観的なもの、孤立は客観的なものとの整理でおおむね違和感はないが孤立にも主観的要素が入り込むのは避けられず、切り分けるのは難しい。
- 孤独感という感情の領域に政府が入り込むことに危うさを感じる向きもあるのではないか。
- 孤独は主観的概念であり、積極面と消極面の両面ある。孤独は愛するものという考え方もあり、孤独を消極面だけで捉えることは危険である。
- 孤独を示す「loneliness」は主観的、心理的に感じるものであり、人とのつながりの欠如と認識。
- 孤独は話を聞いてくれる人がいない、寂しいなど本人が感じている気持ちであり、孤立は居場所がない、一人で問題を抱えているなど、置かれている状況や環境などである。孤独も孤立もその意味の真相はSOSである。
政府は、孤独・孤立の問題を解決していくため、孤独の定義についても議論を進めているようです。
政府調査における孤独の把握方法
内閣官房 孤独・孤立対策担当室によると、令和3年に全国調査が行われています。
調査結果は令和4年4月に「人々のつながりに関する基礎調査」として公表されています。冒頭のグラフは、この調査結果資料から抜粋しました。
この調査では、孤独感を直接質問と間接質問の2種類の質問で把握しています。
直接質問は、「孤独」について直接的に質問しています。
あなたはどの程度、孤独であると感じることがありますか。
- 決してない
- ほとんどない
- たまにある
- 時々ある
- しばしばある・常にある
間接質問は、設問に「孤独」という言葉を使用せずに孤独感を把握する方法です。
3つの質問の合計スコアで孤独感を測ります。
あなたは、自分には人とのつきあいがないと感じることがありますか。
- 決してない
- ほとんどない
- 時々ある
- 常にある
あなたは、自分は取り残されていると感じることがありますか。
- 決してない
- ほとんどない
- 時々ある
- 常にある
あなたは、自分は他の人たちから孤立していると感じることがありますか。
- 決してない
- ほとんどない
- 時々ある
- 常にある
いずれにしても孤独とは、自分がどう感じるか、という主観的な点を評価するしかないようです。

人によって孤独のとらえ方や感じ方が違うので、実態を把握するのは難しそうですね。
トルストイ「アンナ・カレーニナ」における孤独
彼女はもうそれ以上のぞかなかった。馬車のばねの音は聞こえなくなって、鈴の音ばかりがかすかに響いていた。犬のほえ声が、やがて、馬車が村を通り抜けたことを示した、ーそして、そこに取り残されたものは、ただがらんとした野原と、行く手の村と、荒れはてた街道をひとり行く、いっさいのものに縁のない、孤独な彼自身だけであった。
トルストイ「アンナ・カレーニナ」木村浩訳、新潮文庫、中巻86ページ
物語の序盤で、リョーヴィンはキチイにプロポーズし、フラれてしまいます。
リョーヴィンは絶望し、田舎の領地に戻って農村経営に没頭します。
農民たちと心を通わせ一緒になって汗をかくことで、キチイへの気持ちもうすれ、この労働に満ちた生活にこそ人生の意義を見出していきます。
しかし、思いがけずたったひと目キチイを見ただけで、キチイを愛している自分をごまかすことができないことに気付き、孤独を感じたのです。
オブロンスキーは、リョーヴィンのキチイに対する気持ちを次のように表現しています。
つまり、リョーヴィンにとっては、世界じゅうの娘たちは二種類に分かれているのだ。第一は彼女をのぞいた世界じゅうの娘たちで、それらの娘たちはあらゆる人間的欠点をもった、もっとも平凡な娘たちであり、第二の種類は彼女ただひとりで、それはなにひとつ欠点をもたない、いっさいの人間的なものを超越した存在であった。
トルストイ「アンナ・カレーニナ」木村浩訳、新潮文庫、上巻80ページ
この小説は、有名な次の一文で始まります。
幸福な家庭はすべて互いに似かよってものであり、不幸な家庭はどこかその不幸のおもむきが異なっているものである。
トルストイ「アンナ・カレーニナ」木村浩訳、新潮文庫、上巻5ページ
不幸な家庭とは、何かしらバランスがくずれた状態です。
物語の中では2つの不倫、つまりオブロンスキーの不倫とアンナの不倫を想起させます。
逆にいうと、幸福な家庭にはバランスが大事ということです。
そしてこの「バランス」は家庭だけでなく、個人の内面にも応用できます。
バランスが取れた時は幸福を感じ、バランスがくずれた時に孤独を感じるのです。
農村での労働を通して、充実と安らぎを得られると確信したリョーヴィンでしたが、やはり、社会的な文脈だけでなく、愛する者に愛されることも幸福には大事な要素でした。
自分の存在意義を考え続けるリョーヴィンにとって、孤独とは、世界から取り残され、いっさいものに縁がないにも等しい状態なんですね。
 長編小説アンナ・カレーニナを挫折せずに読むための方法まとめ
長編小説アンナ・カレーニナを挫折せずに読むための方法まとめ
ポール・オースター「幽霊たち」における孤独
そこで何をしてたんです?
小説を書いていたのさ。
それだけ?書いていただけ?
書くというのは孤独な作業だ。それは生活をおおいつくしてしまう。ある意味で、作家には自分の人生がないとも言える。そこにいるときでも、本当はそこにいないんだ。
また幽霊ですね。
その通り。
ポール・オースター「幽霊たち」柴田元幸訳,新潮文庫,89ページ
「書くというのは孤独な作業だ。」
これはつまり、「書くというのは、事物を見えにくくする言葉をもって、まるで幽霊のような自分の存在を証明するような作業」だから孤独だという表現です。
言い換えると、書けば書くほど自分の輪郭がぼやけていく、幽霊のように自分が見えないものになっていく感覚、ということでしょう。
この孤独のニュアンスを正確に表現するのは難しいですが、以下の引用が理解のヒントになると思います。
ポイントは、この小説自体はブラックが書いたもの、という視点で読むことです。
出来上がったものを読み直してみると、すべてが正確に思えることを彼は認めざるをえない。なのにどうして、こんなに不安な気持ちが残るんだろう?自分の書いたものを読んで、どうしてこんなに不安な気持ちが残るんだろう?彼はこう思う。何が起きたかを書いたところで、本当に何が起きたのかが伝わりはしないのだ。報告書を書く経験においてはじめて、彼は、言葉がかならず役に立つとは限らないということを思い知る。伝えようとしている事物を、言葉が見えにくくしてしまうことも時にはあり得るのだ。ブルーは部屋の中を見渡し、さまざまな事物に一つずつ注意を集中する。ランプを見て、彼は自分に言う。ランプ、と。ベッドを見て言う。ベッド、と。ノートを見て言う。ノート。ランプをベッドと呼んではならない。そう、これらの言葉は、それが指し示す事物のまわりにすっぽり収まるものなのだ。そうした言葉を口にする瞬間、ブルーは深い満足を覚える。まるで、たったいま自分が、世界の存在を証明したような気がする。それから彼は道の向こうに目を向け、ブラックの部屋の窓を見る。部屋は暗く、ブラックは眠っている。問題はあれなんだ、とブルーは自らを励ますかのように胸のうちで言う。あれ以外の何ものでもないんだ。奴はあそこにいる、だけど奴の姿は見えない。見えたところで、明りが消えているのと変わりはしない。問題はそういうことなんだ。
ポール・オースター「幽霊たち」柴田元幸訳,新潮文庫,30ページ
平野啓一郎「マチネの終わりに」における孤独
孤独というのは、つまりは、この世界への影響力の欠如の意識だった。自分の存在が、他者に対して、まったく影響を持ち得ないということ。持ち得なかったと知ること。
平野啓一郎「マチネの終わりに」,文春文庫,139ページ
孤独を、他者への影響力という言葉で端的に表現しています。
自分の存在が他人にとって何の意味も持たないと認識したとき、孤独を感じるというのはわかる気がします。
なお、この小説は2019年に映画化されています。主演は福山雅治と石田ゆり子です。
平野啓一郎「ある男」における孤独
彼独りしかいないその正方形の空間で、パンチは、そこにいるはずの誰かに向かって放たれ続けている。相手からの攻撃を躱すために、足は絶えず動き続け、上体が細かく左右に揺れた。手応えは、まだ見ぬ対戦相手の肉体にあり、青年は、現在という檻によって、その未来から隔離されている。・・・
原誠も、この寂れたジムで、毎日こんな孤独な練習を続けていたのだろうかと、城戸は想像した。
平野啓一郎「ある男」,文藝春秋,233ページ
「こんな孤独な練習」の「こんな」が指すのは、前段の「現在という檻によって、その未来から隔離されている」状態です。
シャドー・ボクシングは仮想の敵を想定して行うものですので、客観的に見るとひとりぼっちで練習していることには間違いありません。
この時の城戸は、原誠という人物の経歴と境遇をネットなどで調べて知っています。
殺人犯の息子、児童養護施設への入所、万引きの常習で実刑、そしてプロボクサーとしてデビューし、突然の失踪。
自らの出自に苦悩し、未来を描くことができない現在にもがいていたであろう原誠の姿を、城戸はシャドーボクシングに重ねて想像したんだと思います。
孤独とは決して他人との関係だけではないのかもしれません。
時間軸的にとらえると、現在の自分が未来の自分と隔離されていると感じることも孤独と言えるのではないでしょうか。
この小説は映画化が進められており、2022年11年に公開予定となっています。主演は妻夫木聡です。
平野啓一郎「本心」における孤独
用心していても、孤独は日々、体の方々に空いた隙間から、冷たく無音で浸透してきた。僕は慌てて、少し恥ずかしさを感じながら、誰にも覚られないように、その孔を手で塞いだ。
(中略)
自分では、その都度うまく蓋をしたつもりだったが体の隅々の孔が、結局、開いたままで、僕の内側に斑な空虚を作り出していた。僕は、外からの侵入者を警戒するあまり、僕自信が雫れ落ち続けていたことをに、気づいていなかったのだった。
平野啓一郎「本心」,文藝春秋,9ページ
孤独の意味というより、性質や状態を表した文章と言えます。
「僕」は、唯一の家族で最愛の母に突然先立たれ、母のいない誕生日が過ぎて、不安に襲われます。
「孔」は、孤独という侵入者の入り口であり、自我がこぼれ落ちる出口でもある、という比喩表現になっています。

「孔」というイメージに重ねていくところが秀逸ですね。
これは小説の冒頭のシーンですが、終盤には映画タクシードライバーの孤独を表現したセリフを背景に、朔也と三好が語り合う場面が出てきます。
その中で、朔也は岸谷のことを「孤独な人間」と評し、三好は過去の自分の孤独さを「閉じ込められている感じ」と表現しています。
また、もう一人のメインキャラクターのイフィーという人物にしても孤独に描かれています。アバター・デザイナーとして成功しているにも関わらず、両親とは不仲になり、マンションの最上階で冷たい大理石に囲まれて生活しています。
こうしてみると、小説全体が現代の孤独を描き出しているようにも受け取れます。
それぞれの登場人物によって異なる孤独の原因や意味、孤独と向き合う心の変化に注目して読むのもおもしろいでしょう。
カミユ「異邦人」における孤独
一切がはたされ、私がより孤独でないことを感じるために、この私に残された望みといっては、私の処刑の日に大勢の見物人が集まり、憎悪の叫びをあげて、私を迎えることだけだった。
カミユ「異邦人」窪田啓作 訳,新潮文庫,131ページ
小説「異邦人」は「きょう、ママンが死んだ。」から始まるカミユの代表作です。
小説の中で、孤独という言葉が使われているのは、引用したこの最後の一文だけです。
この文章は、主人公ムルソーが「処刑の日に大勢の見物人が憎悪の叫びをあげて、自分を迎えることを望む」という、一見理解不能な文章に見えます。
この一文に限らず、小説全体としても、さまざまな解釈ができます。
私の解釈では、ムルソーはこの世界から失われる幸福な自分に対して、自分が涙をそえたかったのだと考えます。
孤独の辞書的な意味は「仲間や⾝寄りがなく、 ひとりぼっちであること。思うことを語ったり、⼼を通い合わせたりする⼈が⼀⼈もなく寂しいこと。」でした。
ムルソーからは、他人に対して愛おしいとか寂しいという一般的な感情がうかがえません。
- 唯一の肉親である母の死に際しても、涙を流さず、感動を示さなかった。
- ムルソーのことを認めている隣人レエモンから「仲間になりたいか」と聞かれて「どちらでも同じことだ」と返事する。
- 雇い主からパリに転勤しないか?と聞かれ、「結構ですが、実をいうとどちらでも私には同じことだ」と返事する。
- 恋人のマリイから自分と結婚したいかと聞かれ、「それはどっちでもいいことだ」と答える。
一方で、ムルソーに感情がないかというと、そんなことはありません。
疲れた日の翌朝は起きるのがつらいし、映画は面白おかしく、波の中ですり寄せたマリイの体には欲望も感じます。
ムルソーは事実や現象からわき起こる感覚に対して、きわめて素直に反応し、決して嘘をつきません。
ただ、事実や現象に、独断や偏見で意味づけすることを認めないのです。
 カミュ『異邦人』の人物相関図と登場人物の解説
カミュ『異邦人』の人物相関図と登場人物の解説
ムルソーにとって、死というのは自分だけのものです。
ゆえに、死の瞬間とは一人ぼっちで孤独ということになります。
そして、自分が死ぬことについて、泣く権利を持っているのは他人ではなく、あくまで自分だけなのです。
死に近づいて、ママンはあそこで解放を感じ、全く生きかえるのを感じたに違いなかった。何人も、何人といえども、ママンのことを泣く権利はない。
カミユ「異邦人」窪田啓作 訳,新潮文庫,130ページ
死の孤独は、「世界を自分に近いものと感じ」る幸福感によって、ほとんど満たされていました。
死にゆく自分に、より孤独を感じさせないために、泣く権利を使おうとします。
しかし、処刑を前にしてすでに幸福を確信したムルソーは、普通では泣くことができません。
そこで持ち出したのが、泣くための装置である「憎悪の叫び」だったのではないでしょうか。
私に向けられたこの叫びが、あまりに猛烈な勢いで、且つ、検事の視線は全く勝ちほこった調子なので、この数年来はじめてのことだったが、私は泣きたいというばかげた気持ちになった。それは、これらのひとたちにどれほど自分が憎まれているかを感じたからだった。
カミユ「異邦人」窪田啓作 訳,新潮文庫,96ページ
憎悪を感じ、自然と涙する状況を設定することで、孤独を感じることなくおだやかに最期を迎えられると思ったのでしょう。
ヘミングウェイ「老人と海」における孤独
老人は当たりを見わたし、あらためて自分の孤独を痛感した。が、かれは黒々とした深い水のなかに七色のプリズムをのぞき見ることができた。それに眼の前には綱がまっすぐ伸びており、しずまりかえった海洋の不気味なうねりが見てとれる。貿易風にともなって雲がむくむくと立ち昇りはじめた。ふと、前のほうを見ると野鴨の一群が空にくっきりその形を刻みこんだような影を見せて水の上を渡っていく。一瞬影が薄くなる。が、つぎの瞬間にはふたたびくっきりした形をとる。海の上に孤独はない、と老人はつくづく思った。
ヘミングウェイ「老人と海」福田恆存訳,新潮文庫,54ページ
引用したのは、まるまる一つのパラグラフ(段落)です。
「孤独を痛感」するところから始まり、「海の上に孤独はない」と思うまでの一節となっています。
一見なんでもないシーンですが、実はサンチャゴ老人が孤独を乗り越える重要な場面です。
この時、サンチャゴ老人はなぜ孤独を痛感したのでしょうか。
そしてその直後、孤独はないと思うにいたったのでしょうか。
まず、ここにいたるまでの経過をおさらいします。
サンチャゴ老人は、魚が1匹も取れない日が84日続いていました。そのはじめの40日はマノーリンという少年と一緒に漁に出ていました。
そして、サンチャゴ老人は85日目の漁に一人で向かいます。
いつもより遠出したところで、とほうもない大魚がかかり、小舟ごとどんどん沖に引っ張られていきます。
綱を舟に固定すればすぐに切られてしまうため、体重をかけて綱を保持する緊迫した状態が続きます。
綱から手が離せないため、マノーリン少年がいないことを嘆きます。
老人は綱の先の大魚に話しかけます。綱にとまった鳥にも話しかけます。
しかし、大魚は急に綱を引っ張って、海底へ潜っていきます。その勢いで、鳥は飛び立ち、頼りにしていた右手の掌を負傷してしまいます。
綱を左手に持ちかえますが、やがて左手は痙攣を起こして開かなくなってしまいます。
ただでさえマノーリン少年がいなくて寂しいのに、話し相手だった大魚は海深く潜り、鳥は飛び立ち、右手は負傷し、左手はいうことをきかなくなり、いよいよ心細くなったところで「孤独を痛感」したのでしょう。
引用したパラグラフではこの後、サンチャゴ老人が見た情景の描写だけが続きます。
そして、「海の上には孤独はない」と心境が180度変化するのです。
ここに特徴的な情景はありません。
老人にとって目の前の景色は、いつもとなんら変わらない、慣れ親しんだ海だということを再確認したのだと思います。
弱気になっていた自分を客観視し、孤独を乗り越えたのです。

このあと物語はサメとの壮絶な戦いに入っていきますが、その前にあえて孤独を持ってきたことでサンチャゴ老人の英雄的な一面を際立たせています。
物語はほとんどは、サンチャゴ老人が海の上で一人なのに関わらず、「孤独」というワードが出てくるのはこの引用部分だけなのです。
ヘミングウェイはこの「老人と海」を1952年に出版し、1954年にノーベル文学賞を受賞しています。
ヨルシカの楽曲にもオマージュされるなど、今なお読み継がれる名作です。
サン=テグジュペリ「夜間飛行」における孤独
「今夜は、二台も自分の飛行機が飛んでいるのだから、僕にはあの空の全体に責任があるのだ。あの星は、この群集の中に僕をたずねる信号だ、星が僕を見つけたのだ、だから僕はこんなに場違いな気持で、孤独のような気持ちがしたりする」
ある音楽の一節が彼の唇にのぼった。それは、彼が友人といっしょに聞いたあるソナタの一節だった。友人たちには音楽の意味が分からなかったので、「この芸術は、君にも僕にもただ退屈なのだが、ただ君はそれを白状しないだけなんだ」と言った。「そうかもしれない・・・」と彼が答えた。
今夜と同じように、そのときも彼は自分を孤独に感じたが、すぐにまた、このような孤独が持つ美しさを思い知った。あの音楽の伝言は、凡人たちのあいだにあって、秘密のような美しさを持って、彼に、彼にだけ理解されたものだ。あの星の信号もまさにそれだ。それは、多くの肩を乗越えて、彼にだけわかる言葉でものを言っていた。
サン=テグジュペリ「夜間飛行」,堀口大學訳,新潮文庫,58ページ
一度読んだだけでは、よく分からない文章と思うかもしれません。
物語において、危険な夜間飛行を成功させていくことが、支配人リヴィエールの自らに課した使命であり責任です。
リヴィエールは部下に対して常に厳格であり、部下に嫌われることも厭いません。
一方で、理解されない孤独を感じていました。
2台の飛行機が順調に飛行している夜にふと空を見上げたとき、星がまるで自分にしか分からないメッセージを送っていると感じ、孤独のような気持ちがわいてきます。
それは、自分が理解できた音楽を、友人が理解できなかったときに経験した孤独と同じだったのです。このような孤独は秘密のような美しさを持っていると言っています。
星からの信号という比喩だけでロマンチックな美しさを呼び起こしますが、同時に、天命を受け取るような厳粛な交信のようでもあります。
リヴィエールは、この自分だけが理解できることを優越的なこととはとらえていません。
ただ「孤独が持つ秘密のような美しさ」と表現するところに、リヴィエールの人生観が見えてくるような気がします。
ちなみに、サン=テグジュペリはかの有名な「星の王子さま」の作者です。
下重暁子「極上の孤独」における孤独
「犀の角のようにただ独り歩め」
仏陀の言葉である。
(中略)
その意味は、
「サイの頭にある一本の角。その角のように独りで考え、独りで自分の歩みを決めなさい」
(中略)
サイの中でもインドサイは、群れで行動しない。単独で行動するので、「犀の角」とは「孤独」を意味する。
下重暁子「極上の孤独」幻冬舎新書,12ページ
本書は、新書ですので厳密にいうと小説ではなく、エッセイや論評の類いです。「孤独=悪」ではなく、「孤高」「自由」「群れない」といったイメージとともに、孤独を愉しむことを訴えています。
「サイのように」ではなく「サイの角のように」という表現が面白いですね。
獣のツノといえば、シカや牛のように一対2本が多く、1本角のサイは少数派です。
シカや牛のように群れることなく一頭で行動し、その頭にある角は一本だからこそ、ブッダの心をとらえたのかもしれません。
独立した人格を形成していくには、サイの角ように、独りになって自分を見つめる時間が必要なのでしょう。

孤独とは何かを知ることが、孤独を乗り越えるための処方箋の第一歩になると思います。
紹介した小説は、どれもすてきな読書体験が得られる本ばかりです。
ぜひ、手にとって読んでみてはいかがでしょうか。
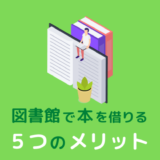 図書館で本を借りて読む5つのメリット|使わないと損
図書館で本を借りて読む5つのメリット|使わないと損